院長先生が陥りやすい「休み」の誤解

歯科クリニックの院長先生に限らず、多くの経営者は日頃の業務に忙殺され、従業員の「休み」について、深く考える余裕がないかもしれません。そのため休日、休暇、休業のそれぞれの意味や定義を正しく理解しているケースはとても少ない…というのが率直な感想です。
しかし、労働基準法が定める「休日」「休暇」「休業」には目的と定義の明確な違いがあり、これらの違いを正しく認識せずに曖昧に運用すると、思わぬ労務コンプライアンス違反を犯したり、場合によっては深刻な労使トラブルに発展しかねません。
そこで本記事では、この3つの「休み」の明確な違いを、社会保険労務士の専門的知見と、かつて医療機関の人事部門で働いていた経験を踏まえて、わかりやすく解説します。この基礎知識が、きっと貴院の健全な経営を守る土台となることでしょう。
休日・休暇・休業は似て非なるもの
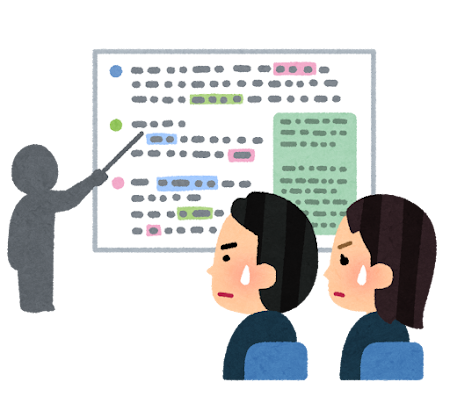
「休日」「休暇」「休業」の最も根本的な違いは、「労働義務がある日か?」と「営業か休業日か?」という2点に集約されます。これらの違いを正確に認識することが、適正な労務管理の第一歩となります。
特に、労働者にとって何が法的な「権利」であるかを理解することが、コンプラ違反やトラブルを未然に防ぐ鍵となります。法律は、労働者が健康で文化的な生活を送り、長く充実した職業人生を全うできるよう、これらの権利を定めているのです。
休日=そもそも労働義務自体がない日
まず「休日」ですが、これはもともと労働義務がない日を指します。歯科クリニック自体が休診日であり、原則として全てのスタッフが就業しようのない状態の日をいいます。
法律上の義務として、事業主は労働者に対し「週に1日以上」または「4週間に4日以上」の休日を与えることが定められています。これを法定休日といい、法定休日にスタッフを労働させることは、原則として違法行為となりますので、注意が必要です。
休暇・休業=労働義務が免除される日
一方で「休暇」や「休業」は、特定の労働者に限り、労働日における労働義務を免除する日を指します。この時、歯科クリニックは通常通り診療を行っており、他のスタッフは勤務しているという点が、休日との大きな相違点です。
休暇には、労働者の法的権利(年次有給休暇等)として定められているものと、事業主が福利厚生として任意で与えるもの(年末年始休暇、お盆休暇等)があり、休業は特定の理由により就業を禁じたり免除したりする措置を意味します。
法定休日と所定休日を正しく理解する

年間休日とは法定休日+所定休日です
休日には、労働基準法で義務付けられた法定休日と、事業主が任意に定める所定休日の2種類があります。法定休日は「1週間に1日」または「4週間に4日」の基準を満たす必要があり、法定休日にプラスして職場独自のルールにもとづき与える休日が所定休日となります。
ところで法定休日と所定休日を合わせて年間何日の休日を付与するのが望ましいのか?と悩まれる院長先生も少なくないでしょう。厚生労働省の令和5年度統計調査によると、全産業の労働者平均では、法定休日と所定休日を合わせた年間日数は115.6日となっているようです。
一般的な歯科クリニックではとりあえずこの水準を参考にし、自院の勤務体系(1年単位の変形労働時間制等)との整合性やワークライフバランスあるいは自己研鑽(学会活動等)などを踏まえて、適切な日数を設定するのが望ましいと思われます。
「振替休日」と「代休」を知らないと
院長先生方が混同しやすいのが「振替休日」と「代休」の違いです。これは、割増賃金が発生するか否かという、人件費に直結する重要な違いがあります。振替休日は、事前に法定休日と労働日を入れ替えることであり、この場合は割増賃金の支払いは不要です。
これに対し代休は、いったん法定休日に労働させた後に事後に休みを与えるもので、すでに法定休日に労働させているため、事業主は割増賃金の支払いが必要となります。この「事前」か「事後」かの違いが、法的な義務とコストに大きな差を生むのです。
許可制の年次有給休暇は法律違反です!

休暇とは、特定の労働者について特定の労働日の労働義務を免除するもので、休暇の取得を希望する労働者が、あらかじめ使用者に対して許可申請するのが一般的なルールです。注意すべきは法律で定められた休暇については、許可制にすると法令違反となることです。
以下の休暇は労働基準法や育児・介護休業法に定められた労働者の権利であり、使用者は労働者がこれらの休暇を取得することを拒否できません。判例はこれらの休暇の取得を使用者の許可制としたり、取得に際して休暇の理由を届出させることは認められないとしています。
年次有給休暇
年次有給休暇は、雇入れ後6ヶ月を経過し、その期間の所定労働日の8割以上出勤した労働者に、年10日以上付与することが事業主に義務付けられています。労働者の請求があれば、その取得を拒否することはできず、これが労働者の法的権利たるゆえんです。
取得促進のため、年間5日については時季を指定して取得させることが義務化されており(年10日以上付与される労働者に限る)、未達の場合は罰金刑が科されます。制度の詳細は別の記事で解説しますが、日頃から年次有給休暇を取得しやすい職場環境づくりが必要です。
子の看護休暇・介護休暇
育児介護休業法に基づく子の看護休暇と介護休暇もまた、法律上の労働者の権利です。未就学児を養育する労働者や家族を介護する労働者は、それぞれ年5日間まで取得が可能で、こちらも使用者の許可や承認は不要です。
特筆すべきは、これらの休暇は半日や時間単位での取得も可能であり、パートタイム労働者にも公平に与えられるべき点です。この柔軟な制度の理解が、特に女性スタッフの多い歯科クリニック業界における人材の定着にも繋がります。
生理休暇
労働基準法に定められる生理休暇は、生理日の就業が著しく困難な女性が請求した場合、事業主はその女性を就業させてはなりません。こちらも取得にあたって医師の診断書等は不要であり、取得日数に上限を設けることもできません。
半日や時間単位での付与も可能ですが、その運用は女性スタッフのプライバシーに配慮し、慎重に行う必要があります。
代替休暇
労働基準法は、月60時間を超える法定時間外労働に対し、通常の時間外割増の25%に加え、25%の割増賃金を上乗せして支払う義務を定めています。代替休暇は、上乗せ部分の25%の支払いに代えて、年次有給休暇とは別に有給休暇を付与できる制度です。
これは時間外労働の抑制を促す政策的な制度であり、例えば60時間超の残業が10時間であれば、割増率25%に代わる形で2.5時間の代替休暇を付与することが可能です。一般的な歯科クリニックではレアケースと思われますが、休暇制度のひとつとして知っておきましょう。
休業には長期の労働免除と就業禁止がある

休業は、労働者に対して就業を免除したり、禁じたりするものです。これは、特定のライフイベントや予期せぬ事態に対応するための重要な制度であり、特に産前産後休業や育児介護休業は、スタッフのキャリア継続を支える上で不可欠です。
産前産後休業
労働基準法に基づく産前産後休業は、特に産後の対応が重要です。産前休業は出産予定日の6週間前から、本人が請求し、就業を希望しない場合に休業させればよいのに対し、産後休業は出産日から8週間を経過しない女性を原則として就業させてはならないとされています。
産後休業は本人の意向に関わらず適用される就業禁止規定であり、使用者の一方的判断で労働させることはできません。
育児・介護休業
育児介護休業は、育児介護休業法に基づき、1歳未満の子を養育する労働者は子が1歳に達するまで、家族を介護する労働者は最長93日間まで休業が可能です。育児休業は男性労働者も対象であり、これも法定の権利であるため、取得に際して使用者の承認は不要です。
特に政府は男性労働者の育休取得を促進しており、令和4年10月には出生時育児休業(産後パパ育休)制度も創設されました。
労災による休業
業務上の傷病により労働者が医師から就労不能と診断された場合、使用者は負傷あるいは疾病に罹患した労働者について、療養に必要な期間を休業させなければなりません。
なおスーパー業界ではシニアスタッフの労災認定が増加中ですが、人手不足が深刻な事業者では労災申請しても休業させず、そのまま働かせる悪質なケースが問題になっています。このような場合、経営者は労働契約法上の安全配慮義務違反に問われる可能性があります。
就業禁止による休業
労働安全衛生法および労働安全衛生規則は、労働者が伝染性の病気に罹患した場合、あるいは心臓、腎臓、肺等に疾患を抱える者で、就労によって病勢が著しく悪化する恐れのある者を、就労させてはならないと定めています。
感染症法も、次の感染症に罹った労働者の就労を禁じています。なおこれらは事業主都合の休業ではない(労働者側の事情によって労務を提供できない状態)ため、当該労働者に対する休業手当の支払いは不要です。
- 一類感染症(エボラ出血熱、ペストなど)
- 二類感染症(結核、SARSなど)
- 三類感染症(コレラ、細菌性赤痢など)
- 新型インフルエンザ等感染症
- その他、指定感染症(過去の新型コロナウイルス感染症のように政令で指定されたもの)
制度の見直しは社労士にご相談ください

以上、雑駁でしたが「休日」「休暇」「休業」の違いについて駆け足で解説して参りました。まず経営者たる院長先生ご自身が、それぞれの「休み」の目的と性質、要件などの基本ルールを把握していないと、思わぬトラブルに発展するリスクがありますので要注意です。
近年は少子高齢化の加速やワークライフバランス推進などの時代的背景もあって、「休み」に関する制度や政策は、年々多様化・複雑化の一途を辿っています。もし自院の就業ルールを整理整頓し、効果的に運用したいとお考えの際は、我々社労士にお気軽にご相談ください。
お問い合わせはこちらから

リモートワークスコンサルティング社労士事務所


私たちは社労士事務所ですので就業規則や労使協定の作成および届出代行のほか、煩雑な社会保険や労働保険の事務代理もできます。オンライン特化型なのでスピーディでリーズナブル。電子申請に強く、SRP2認証も取得済みなので安全・安心です。
道内の開業医の先生であれば北海道中小企業総合支援センターの専門家派遣事業(公費による専門家派遣サービス)もご利用可能です。お問い合わせやお仕事のご依頼などは、こちらのフォームからお気軽にどうぞ(追って担当者からご連絡いたします)。



