法定労働時間の例外は36協定だけではない

社労士の山口です。今回は法定労働時間の例外的勤務形態である「変形労働時間制」の基本概要をご説明させていただきます。変形労働時間制は、法定労働時間を弾力的に運用することで、労働生産性向上や人件費抑制に効果的な制度であり、医療業界でも一応導入可能です。
ただし一般的な歯科クリニックでは、診療予約に基づく医療スタッフの配置が基本なので、全ての変形労働時間制がマッチするわけではありません。例えば、労働者が自由に始業や終業の時間を決められるフレックスタイム制などは、歯科診療に適合しづらい側面があります。
本記事では、歯科クリニックでも活用できそうな「1年変形」と「1ヶ月変形」の詳細な解説(別記事)に先立ち、まずは変形労働時間制の概念と法定の4つの制度のそれぞれの特徴、導入メリット、そして運用上の重要な注意事項を、簡潔にお伝えいたします。
変形労働時間制を導入する経営上のメリット
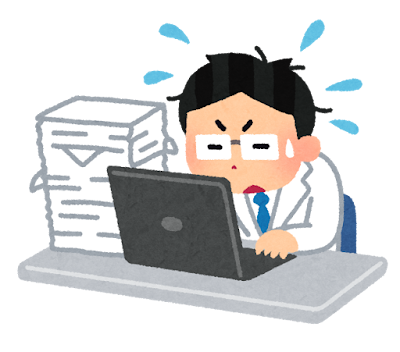
変形労働時間制のメリットは、業務の繁閑に応じて労働時間を調整できる点です。たとえば閑散期の勤務を6時間にする代わりに、繁忙期を10時間とした場合、通常は8時間を超える勤務は法定外残業となりますが、本制度では法定内労働時間として取り扱うことができます。
これにより閑散日の手待ち時間に無駄な給与を支払う必要がなく、逆に繁忙日は事前に延長した労働時間までは割増賃金の支払いが免除されます。また従業員にとっても閑散日はさっさと退勤できるため、ワーク・ライフ・バランスの実現に大きく役立ちます。
適正な人件費コントロールによってクリニックの資金繰りが改善されると同時に、従業員満足度を高めることで、雇用の安定と定着が促進されます。繁忙日と換算日を明確にすることで、働き方にメリハリが生まれ、職場の労働生産性も改善されるでしょう。
4つの変形労働時間制のそれぞれの特徴とは?

1年単位の変形労働時間制
1年単位の変形労働時間制は、1ヶ月以上~1年以内の範囲で有効期間(本制度の適用期間)を定め、有効期間の週平均労働時間が40時間以内に収まっていれば、特定の日に法定労働時間を超えて従業員を就労させることができます。季節により繁閑が生じる業種に適しています。
注意すべきは1年単位の変形労働時間制を導入しても、労働時間の上限は1日10時間以内、1週間52週間以内です。これを超える場合は、36協定の締結&届出および割増賃金の支払いが必要です。また有効期間が3ヶ月以上の場合、年間労働日数は280日以内でなければなりません。
1ヶ月単位の変形労働時間制
1ヶ月単位の変形労働時間制は、1ヶ月以内の期間を平均し、週の平均労働時間が40時間以内であれば、特定の日に法定労働時間を超えて従業員を就労させられる制度です。毎月、特定の時期(例えば給料日や月末など)に業務が繁忙となる業種に適しています。
1ヶ月単位の変形労働時間制の場合、1日あたりの労働時間の上限などは設けられていません。1年単位の変形労働時間制を導入すると、法定労働時間の特例(10人未満の歯科クリニック=週44時間まで)が認められませんが、1ヶ月変形では法定労働時間の特例も併用可能です。
1週間単位の非定型的変形労働時間制
1週間単位で労働時間を柔軟に設定できる制度です。週のうち特定の曜日に業務の繁閑が生じる業種に適していますが、実施できるのは従業員30人未満の小売業、旅館業、料理店、飲食店に限られます。残念ながら医療業は対象外なので、あくまでも参考までにご覧ください。
注意すべきは、1年変形同様に、本制度を導入した場合には、前述の法定労働時間の特例(法定の業種のうち従業員10人未満の事業場=週44時間まで)は適用されません。事業の特性に応じて、1週間変形か法定労働時間の特例のどちらか一方を選択しなければなりません。
フレックスタイム制
1ヶ月超〜3ヶ月以内の清算期間において、労働者が日々の始業・終業時刻を自由に決められる制度で、子育てや介護をされている労働者にとって、非常に働きやすい制度として注目されています。なお始業と終業の片方のみ裁量権を与えるような運用は認められません。
清算期間が1ヶ月を超える場合は、週の労働時間の上限を50時間以内に収めなければなりません。なお医療業において、フレックスタイム制を導入することは現実的ではありません。急患や急変などがあった場合に、必要なマンパワーを確保できないといった事態に陥ります。
変形労働時間制のキホンのまとめ

厳密には変形労働時間制は、1年単位、1ヶ月単位、1週間単位の場合3種類です。これらに共通する特徴は、任意の期間における週の平均労働時間が法定労働時間(40時間/週)内に収まっていれば、特定の日に法定労働時間(8時間)を超えて従業員を就労させられる点です。
変形労働時間制の導入により、人件費を抑えつつ、業務の繁閑に応じた柔軟な人員配置が可能となります。ただし、変形労働時間制の実施に際して、事前に勤務計画を作成し従業員に周知しておかねばならない点に注意です。その時々で労働時間を変更するような運用はNGです。
なお労働基準法では、労働者に対して年5日以上の年次有給休暇を付与する義務を事業者に課しており、未達には厳しい罰則が適用されます。そこで勤務計画を作成する際に、予め年次有給休暇の取得予定も組み入れておくことで、法令違反の防止効果も期待できるでしょう。
お問い合わせはこちらから

リモートワークスコンサルティング社労士事務所


私たちは社労士事務所ですので就業規則や労使協定の作成および届出代行のほか、煩雑な社会保険や労働保険の事務代理もできます。オンライン特化型なのでスピーディでリーズナブル。電子申請に強く、SRP2認証も取得済みなので安全・安心です。
道内の開業医の先生であれば北海道中小企業総合支援センターの専門家派遣事業(公費による専門家派遣サービス)もご利用可能です。お問い合わせやお仕事のご依頼などは、こちらのフォームからお気軽にどうぞ(追って担当者からご連絡いたします)。



