労働時間の正しい定義知ってますか?

労働時間の管理は労務管理のキホン中のキホンであるということについて異論を唱える方はいないと思います。昨今、働き方の多様化が進み、労働法制も変化する中で、労働時間に関する正しい知識と運用は、有能な人材の採用および定着に直結することは間違いありません。
労働時間とは「労働者が使用者の指揮命令下に置かれた状態にあり、その時間を労働者の任意で自由に使うことができない時間」をいいます。つまり就業規則や労働契約で定められた「始業~終業」の時間帯に限らず、次の時間も労働時間に含まれるので注意が必要です。
- 更衣室で制服に着替える時間
- 始業前の朝礼
- 終業後の後片付けや清掃
- 全員参加を前提とした研修会や懇親会
これらは、労働者が家事や余暇など自由に利用できない時間すなわち労働時間なので、事業主は労働者に賃金を支払う義務が生じます。
医療業界でありがちな残業に対する誤解

高度専門職の集団である医療業界では弛まぬ研鑽がつきものであり、また「患者さんのために」という強い職業倫理もあり、スタッフに対して終業後の勉強会参加や病棟のレクリエーションあるいは健康講座などの手伝いを、無給で行わせている医療機関は少なくありません。
かつて私が医療機関に勤務していた際に、これらがサービス残業に該当すると指摘したところ、看護部長から「本人のスキルや知識を高めるための研鑽の機会を与えてやっているのに、なぜ残業手当まで払う必要があるの?」と逆に問い詰められた経験があります。
しかし、これはあくまで看護部長さん個人の価値観であり、労働法令上では、労働者に「出欠を決める裁量権」があるかどうかがポイントです。職務命令として強制参加である場合や、参加しないと業務に支障が出るような研修であれば、労働時間とみなすのが正解です。
特に医療機関ではこのような誤解が生じがちで、これがサービス残業の温床となり、労務コンプライアンス違反につながります。自院のスタッフが安心して働き、最高のパフォーマンスを発揮できるよう、労働時間の定義を正しく理解し、運用することが大切なのです。
法定労働時間と所定労働時間のちがい

労働時間には、大きく分けて法定労働時間と所定労働時間の2つの概念があります。
- 法定労働時間
- 労働基準法で定められた労働時間の上限です。原則として「1日8時間、1週間40時間」と定められています。
- これを超える労働(法定外残業)をさせるには、労働基準法第36条に基づく労使協定(いわゆる36協定)の締結と、労働基準監督署への届出が必須です。これらがないまま残業や休日出勤をさせると、労働基準法違反となり厳しい罰則が適用されます。
- なお従業員10人未満の歯科クリニックは、特例事業として週の法定労働時間が44時間までとされています。
- 所定労働時間
- 法定労働時間の範囲内で、事業主が独自に定めた契約上の労働時間をいいます。
- 例えば「月~金が7時間勤務で土曜が5時間勤務」など。1日あるいは週の合計が法定労働時間内に収まっていれば問題ありません。
法定労働時間を超える法定外残業には、所定の率で計算した時間外割増手当を支払う義務が生じますが、これについては別の記事で解説します。
複業・副業者の労働時間の計算ルール

近年は働き方の多様化とともに、複数の職場をかけもちして働くケース(複業・副業)が増えています。この傾向は勤務歯科医師や歯科衛生士、歯科技工士、事務員なども同様ですが、こういった働き方の場合、それぞれの職場で働く労働時間を通算する必要があります。
例えば、自院のスタッフが副業している場合、院長先生は副業先の労働時間を通算して、法定労働時間(原則8時間/日、40時間/週)を超えていないかを確認しなければなりません。他の職場の勤務時間の把握は使用者の義務ですが、把握方法は労働者本人の申告によります。
具体的な通算ルールは以下の通りです。
所定労働時間の通算
労働契約を結んだ順で通算
(例)
- A歯科;就労R5年。所定15時~19時(4H)
- B歯科;就労R7年。所定09時~14時(5H)
A歯科(4H)→B歯科(5H)の順で労働時間を通算します。法定労働時間(8H)を超過した1Hは、B歯科で発生した法定外残業となります。
所定”外”労働時間の通算
残業が発生した時間順で通算
(例)
- C歯科;所定09時~12時(3H)+残業1.5H
- D歯科;所定13時~16時(3H)+残業1.5H
C歯科の残業(1.5H)→D歯科の残業(1.5H)の順で通算しますので、法定労働時間(8H)を超過した1Hは、D歯科で発生した法定外残業となります。
法定労働時間が適用されない労働者

労働基準法では、法定労働時間に関するルールの適用が除外されている労働者も存在します。主な例外は以下の通りです。
- 農林水産業に従事する者
- 管理監督者
- 機密の事務を取り扱う者(社長秘書など)
- 特殊な労働形態の者(監視・断続的労働に従事する者、宿日直勤務に従事する者)
特に注意すべき点
- 管理監督者: 役職名ではなく、職務内容、権限と責任、処遇などの実態で判断されます。店長という肩書でも、自身の就労時間について自由な裁量権がなく、他のスタッフと同じ勤務シフトで店内業務を行うような場合は、管理監督者とはみなされません。
- 医師の当直: 一般的に、医師の当直勤務は「宿日直勤務」の適用除外許可の要件(ほとんどが手待ち時間で、実作業がほとんどないこと)を満たさない場合が多く、急患・急変など突発的な対応が頻繁に発生するため、通常の労働時間の延長とみなされます。
- 深夜残業と年次有給休暇: この適用除外規定は、あくまで「勤務時間数」に関するルールであり、深夜勤務(勤務時間帯)と年次有給休暇のルールは除外されません(つまり管理職であっても深夜割増手当の支払いと年次有給休暇の付与が必要です)。
労働時間管理の目的と適正な記録

実は意外と人事担当者も見落としていることがあります。それは労働法令によって労働時間管理の目的と記録の方法は、次のように大きく2つあるということです。
- 労働基準法
目的;法定労働時間の遵守、残業抑制、時間外や深夜割増賃金の計算
記録;原則はタイムカード等による記録だが使用者の現認(出退勤の目視確認)でも可 - 労働安全衛生法
目的;産業医への報告および医師面接の対象となる長時間労働者(月80H)の把握
記録;タイムカード、ICレコーダー、PCのログなど機器を介した客観的な方法に限る
注目すべきは労働安全衛生法の労働時間管理の目的は労働者の健康管理なので、管理職も出退勤の記録が必要ということです。実務ではより厳格な労働安全衛生法の基準にあわせて、管理職も含めてタイムカードなどで労働時間の記録を行うケースが一般的です。
ワークライフバランス実現の取り組み
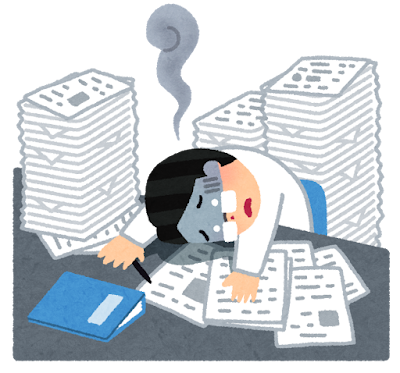
Z世代は、仕事とプライベートの適度なバランス(ワークライフバランス)を重視する傾向が強いと言われています。それを後押しするように労働時間等設定改善法および改善指針では、事業主に対して職場の時短や年次有給休暇の取得促進の努力義務を明示しています。
- 労働時間等設定改善委員会(労使間で時短勤務について話し合う場)の設置
- 年次有給休暇を取得しやすい環境の整備
- ノー残業デーやノー残業ウィークの導入
人生の大部分の時間を勤務先で過ごすという昭和時代の職場慣行は、多様な働き方や介護・子育ての両立が求められる現代社会にそぐわない価値観であるのみならず、ダラダラとした居残り残業が日本の労働生産性を低迷させている元凶だという指摘もあります。
また労災保険法(労働者災害補償保険法)では、過重労働に起因する脳・心疾患あるいは精神疾患が労災認定される場合の労働時間の基準が明記されています。活気ある健康的な職場づくりにおいて、従業員のワークライフバランスの追求は必須の課題といえそうです。
労働時間管理のキホンのまとめ

本記事では、労働時間管理が労務管理の大原則であり、その根幹が法定労働時間であることを解説いたしました。院長先生方におかれましては、労務コンプライアンス違反を防ぐため、自院のスタッフの労働時間を適宜チェックし、適切にコントロールしましょう。
また、法定労働時間を遵守するだけでなく、仕事とプライベートの両立、すなわちワークライフバランスの実現に向けて、業務の合理化や勤務時間の短縮、年次有給休暇の取得促進などを図ることは、優秀な人材の採用と定着の有効策となりうるのです。
もっとも労働時間の管理は複雑であり、最新の法令に則った対応が求められます。もし、自院の労働時間管理についてお悩みやご不明な点がございましたら、人事労務の専門家である社会保険労務士にどうぞお気軽にご相談ください。
お問い合わせはこちらから

リモートワークスコンサルティング社労士事務所


私たちは社労士事務所ですので就業規則や労使協定の作成および届出代行のほか、煩雑な社会保険や労働保険の事務代理もできます。オンライン特化型なのでスピーディでリーズナブル。電子申請に強く、SRP2認証も取得済みなので安全・安心です。
道内の開業医の先生であれば北海道中小企業総合支援センターの専門家派遣事業(公費による専門家派遣サービス)もご利用可能です。お問い合わせやお仕事のご依頼などは、こちらのフォームからお気軽にどうぞ(追って担当者からご連絡いたします)。



