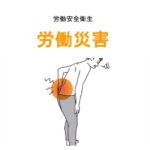スタッフの労災事故、適切に対応できていますか?
日々の診療とクリニック経営で多忙を極める歯科クリニックの院長先生にとって、スタッフの安全管理も重要な責務の一つです。
診療室での転倒事故、診療器具による怪我など、残念ながら予期せぬ労働災害を完全に避けることは困難です。
このように万が一の事故が発生した際、労災保険の給付申請とは別に「労働者死傷病報告」という手続きが必要なことをご存知でしょうか。
労災保険の手続きは行ったものの、労働者死傷病報告は未提出というケースが少なくありません。
この報告を怠ると法的なリスクを負う可能性があるため、しっかりと理解しておく必要があります。
労働者死傷病報告とは?労働安全衛生法に基づく事業主の義務
労働者死傷病報告は、労働安全衛生法および労働安全衛生規則に基づき、事業主に義務付けられている重要な手続きです。
手続きは、規定の様式を労働基準監督署に提出することで行います。
「小さな歯科クリニックだから関係ないだろう」と思われがちですが、常勤・非常勤、正社員・パート・アルバイトといった雇用形態を問わずスタッフをたった1人でも雇用していれば、クリニックの規模に関わらず、報告義務が生じます。
この報告制度は、労働災害の発生状況を国が把握し、類似災害の防止策を検討するための基礎データとして活用されます。
個々の事業所の安全対策だけでなく、全ての職場の安全性向上にもつながる、社会的意義のある制度です。
労働者死傷病報告を怠ると、労働安全衛生法違反として、50万円以下の罰金が科される可能性があります。
労働者死傷病報告が必要になるケースとは?
労働者死傷病報告は、労働者が労働災害によって「死亡」または「休業」した場合に提出が必要です。
なお、休業を伴わない労災や、通勤中の事故(通勤災害)は報告の対象とはなりません。
労働者死傷病報告の提出方法と手続きの流れ
提出期限
提出期限は災害の程度により異なります
- 死亡および4日以上の休業の場合
- 遅滞なく提出
- 4日未満の休業の場合
- 四半期ごとにまとめて報告
| 労災発生日 | 提出期限 |
|---|---|
| 1月~3月 | 4月30日 |
| 4月~6月 | 7月31日 |
| 7月~9月 | 10月31日 |
| 10月~12月 | 1月31日 |
①と②で届出の様式が異なりますので、注意が必要です。
提出先
クリニックの所在地を管轄する労働基準監督署へ提出します。
なお、労働者死傷病報告は、2025年1月から電子申請による提出が義務化されています。
提出方法
厚生労働省の「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」から、様式の作成と電子申請を行います。
労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス(厚生労働省)
電子申請には下記いずれかのアカウント・IDが必要です。
- e-Govアカウント
- GビズID
- Microsoftアカウント
電子申請が困難な場合は、当面の間、書面による報告も可能です。
・労働者死傷病報告(死亡・休業4日以上)様式
・労働者死傷病報告(休業4日未満)様式
記入すべき主な項目
- 事業場の基本情報(名称、所在地、業種など)
- 被災者の情報(氏名、年齢、雇用形態、経験年数など)
- 災害の発生状況(発生日時、場所、原因、経過など)
- 災害の程度(傷病名、休業見込み期間など)
電子申請では、災害発生時の略図の画像データの添付が求められます。事前に準備しておきましょう。
報告のポイント:よくある疑問を解消します
パートやアルバイト、派遣社員が労働災害で死亡・休業した場合も報告は必要ですか?
はい、雇用形態に関わらず、そのスタッフが労働者であれば報告が必要です。
なお、派遣社員の場合は派遣先(歯科クリニック)と派遣元(派遣会社)の両方が報告義務を負います。そのため、提出した労働者私傷病報告の写しを派遣元に送付する必要があります。労災保険の給付手続きとは別に報告が必要なのですか?
はい、労災保険の給付申請とは別に、労働者死傷病報告も行う必要があります。
軽症の場合でも報告は必要ですか?
軽症であっても、1日でも休業すれば報告対象となります。ただし、4日未満の休業の場合は四半期ごとにまとめて報告することとされています。
歯科クリニックの労務管理は専門家にお任せください
「労働者死傷病報告」は、いざという時に必要となる重要な事務手続きです。普段馴染みのない手続きだからこそ、その時になると戸惑ってしまうことが多いのではないでしょうか。
また、2025年1月から義務化された電子申請への対応も求められます。
診療業務で多忙な中、このような慣れない事務手続きを並行して進めるのは、大きな負担となるでしょう。
安心して診療や経営に集中できる環境を整えるためにも、煩雑な事務作業は、社会保険労務士のような専門家に任せてみませんか?
当事務所では、労働保険・社会保険の手続き代行をはじめとして、労務管理全般をサポートいたします。
「労働者死傷病報告の提出だけを依頼したい」といった、ピンポイントでのサポートも承っております。
まずはお気軽にご相談ください。
お問い合わせはこちらから

リモートワークスコンサルティング社労士事務所


私たちは社労士事務所ですので就業規則や労使協定の作成および届出代行のほか、煩雑な社会保険や労働保険の事務代理もできます。オンライン特化型なのでスピーディでリーズナブル。電子申請に強く、SRP2認証も取得済みなので安全・安心です。
道内の開業医の先生であれば北海道中小企業総合支援センターの専門家派遣事業(公費による専門家派遣サービス)もご利用可能です。お問い合わせやお仕事のご依頼などは、こちらのフォームからお気軽にどうぞ(追って担当者からご連絡いたします)。



おすすめの書籍
労働安全衛生法と、同法に基づき事業者が具体的に行うべきことが分かる解説書。最新の法改正にも対応しています。
イラストや図表も豊富で、理解が進む一冊です。