労務コンプライアンスはCSRの最低限
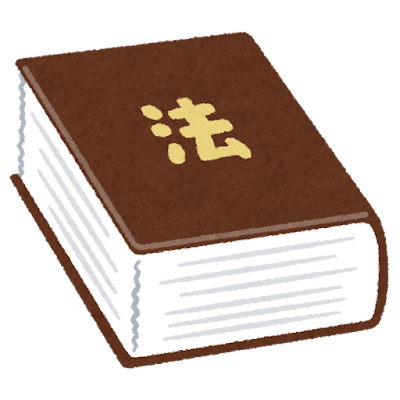
医療経営において、法令遵守を意味するコンプライアンスは必須条件です。これは医療機関に限らず、一般企業でもコンプライアンスの確立なくして、持続的な事業の成長と発展はないのが常識となっています。
企業がコンプライアンスに取り組むのは、国家や社会の一員として事業活動を行う上での最低限のルールだからです。自社の利益ばかりを追求し、従業員や地域への配慮を怠る経営姿勢では、社会的な支持を失い事業継続は困難になります。多くの企業が熱心に取り組むCSR(社会的責任)の最低ラインが、このコンプライアンスに他なりません。
そして、労務コンプライアンスとは、企業経営の人事マネジメント領域において、労働法令を遵守することです。ヒト・モノ・カネの3大経営リソースのうち、人的資源を有効活用する人事マネジメントの根幹を成すのが、この労務管理であり、労務コンプライアンスなのです。
労働基準法を甘くみると大変なことに…

労務コンプライアンスと聞いて、多くの方が労働基準法をイメージされるでしょう。この法律は労働法令の中核的な基本法であり、労使関係で弱い立場に置かれがちな労働者の人権を守るために、事業主がしてはいけない禁止事項や守るべき義務を明文化したものです。
元々、民事不介入を旨とする民法の雇用契約条項から派生した労働基準法ですが、その最大の特徴は行政取締法規であり、強行規定である点にあります。労働契約においては、たとえ労使間で合意があったとしても、労働基準法に違反する劣悪な労働条件は無効とされ、違反した事業主には懲役刑や罰金刑などの厳しい処罰が科されます。
ところで、昭和22年の労働基準法の制定から80年近くが経ち、日本の労働環境は大きく変化しました。この社会の変化に対応すべく、労働基準法自身も数度の改正を重ねています。さらに、労働契約法、労働安全衛生法、育児・介護休業法などが次々と誕生し、労働基準法を補完し、特定の条項を拡充する役割を果たしています。
労務コンプラが必須となった時代背景

現在は終身雇用制が事実上終焉を迎え、雇用の流動化が進んでいます。ライフスタイルの多様化に伴い、人々の就労に対する価値観や就労形態も多様化し、それに伴って労働法制や労務管理も複雑化しているのが現状です。
現代社会において決定的なのは、コンプライアンス違反の企業が「ブラック企業」というレッテルを貼られ、SNSなどで世間に瞬く間に拡散されるようになったことです。また難しい法律知識もインターネットでAI検索することで、誰でも容易に理解できるようになり、昭和の頃のような経営者と労働者との間の情報格差は無くなってきています。
そして、今後はいよいよ労働力人口が本格的に減少に転じる局面に入りますが、特に若手世代であるZ世代は、ブラック企業を強く避ける傾向があります。このような背景から、優秀な人材を確保し、定着させるためにも、労務コンプライアンスの確立は多くの事業者にとって避けて通れない最重要の経営課題となっています。
労務コンプラ違反放置の代償は大きい

労務コンプライアンス違反を放置することは、経営に深刻なリスクをもたらします。労働基準監督署の臨検で違反が認められた場合、違反事業者として社名がインターネットで公表されることがありますし、ハローワークでは求人を受理してもらえなくなる恐れもあります。
さらに、労災事故が続けば特別安全衛生計画の指定事業場となり、労災保険料率がアップします。また、雇用関係の助成金なども利用できなくなってしまいます。最悪の場合、従業員が地域合同労組に駆け込み、団体交渉を申し入れてくる事態に発展することもあるでしょう。
企業イメージの低下は避けられず、高度専門職や若手人材の獲得が困難になります。その結果、既存社員の離職率が上がるばかりでなく、場合によっては営業エリアでの不買運動に発展するなど、事業存続に関わる重大なリスクを招くことになります。
歯科クリニックこそコンプラチェック

労務コンプライアンスを確立するには、まず労働関係法令を広く理解することです。その上で、法令違反とならないように自社の就業ルールを見直し、労務管理の体制をしっかりと整備することが重要です。そして、職位や職責に応じた労務コンプライアンス教育を継続的に行うのがセオリーです。
特に医療業界は、患者さんの生命や健康に直結する高度専門職の集団であり、人材の質の良し悪しがクリニック経営にダイレクトに反映されます。そのため、有能な人材の定着を促すためにも、適正な労務コンプライアンスの確立は不可欠です。
全国の歯科クリニックの平均的な従業員数は4.6人です。就業規則の作成・届出義務がないことから、労務コンプライアンス体制の整備がおろそかになりがちです。しかし、就業ルールを明確にせず、スタッフの安全衛生に無頓着では、有能な人材など定着しません。
そこで当事務所では、企業の労務コンプライアンス実施状況を専門家である社労士が診断し、「ホワイト企業」のお墨付きである社労士診断認証の取得をサポートしています。この認証マークは、採用ページや求人広告などに表示することで、人材を大切にする職場であることを広くアピールする上で大変有効です。

ビジネスと人権時代の経営姿勢とは?
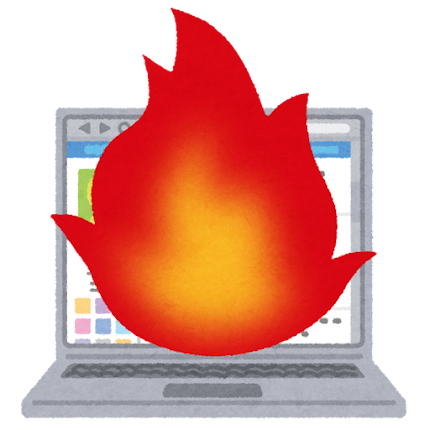
医療業界には、医師を頂点とするパターナリズムや、看護師の「お礼奉公」といった、現代の労働法制とは異なる独特の職場慣行が色濃く残る側面があります。これが、時にはパワハラや未払い残業代といった労務コンプライアンス違反を引き起こす原因となることがあります。
誤った職場慣行やコンプライアンス違反を容認したために、世間から猛バッシングを受け、経営難に陥る老舗ブランド企業が後を絶たないことはご存知の通りです。「これくらいなら大丈夫だろう」という甘い考えが、労務コンプライアンス違反をエスカレートさせ、社会に拡散し炎上することで自院が存続できなくなることも充分ありえます。
現在、法曹士業の界隈では「ビジネスと人権」というテーマが注目されています。誰かの犠牲(人権侵害)の上に成り立つビジネスは言語道断というのが常識であり、そのようなビジネスは淘汰されてしまえという風潮にあります。労務コンプライアンスへの真摯な取り組みこそが、クリニックの持続的な成長と発展を可能にする唯一の道なのです。
お問い合わせはこちらから

リモートワークスコンサルティング社労士事務所


私たちは社労士事務所ですので就業規則や労使協定の作成および届出代行のほか、煩雑な社会保険や労働保険の事務代理もできます。オンライン特化型なのでスピーディでリーズナブル。電子申請に強く、SRP2認証も取得済みなので安全・安心です。
道内の開業医の先生であれば北海道中小企業総合支援センターの専門家派遣事業(公費による専門家派遣サービス)もご利用可能です。お問い合わせやお仕事のご依頼などは、こちらのフォームからお気軽にどうぞ(追って担当者からご連絡いたします)。



