法定休日のキホンを理解する
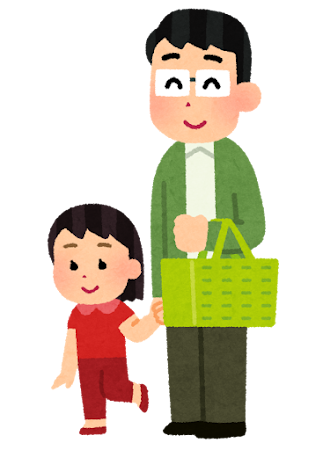
法定休日の付与は義務
労働基準法は、事業主および使用者は、労働者に対し、毎週少なくとも1日の休日を与えることを義務付けています。この法令によって義務化された休日を法定休日といいます。
また、法定休日を与える際は、4週間を通じ4日以上の休日を与える方法でも可能としています。法定休日の条文をそのまま適用すると、4週間のうち最初の4日間を法定休日とし、残りの24日間を連続勤務させてもよいことになります(非現実的な運用ですが…)。
法定休日は何曜日か?
実は労働基準法や労働基準法施行規則は、法定休日の具体的な曜日を特定していません。したがって法定休日を何曜日とするかは、それぞれの事業主が任意で決定することができます。
もし法定休日の曜日を特定しなかった場合は、日曜日を法定休日とみなします。一方で自院の法定休日の曜日を明確に定めた場合は、就業規則に明記し、自院のスタッフに周知しなければなりません。
法定休日があいまいだと…
ところで従業員10人未満の事業場は就業規則の作成義務がありません。したがって就業規則を作成していない事業場の場合は、法定休日=日曜日となります。法的には不可能なのであくまでも仮定の話ですが、もし法定休日が不明確だとどんなリスクが生じるでしょうか?
一般的に開業歯科クリニックは、医療圏あるいは所属する歯科医師会ごとに休日診療の輪番制に参加しているケースが多いです。したがって日曜日に自院のスタッフを出勤させた場合、法定休日労働の割増賃金を適正に計算できなくなり、未払い賃金が発生してしまいます。
法定休日は何時から何時までか?
労働基準法には、法定休日の開始と終了に関する規定は明記されていません。しかし、厚生労働省の通達によると、法定休日は午前零時から24時までの1日とされています。ここで注意すべきは「労働日の1日」と「法定休日の1日」を混同しないことです。
労働日の1日を何時から始業し、何時をもって終業とするかは、就業規則に定めることで、院長先生が自院の都合に応じて任意に設定することができます。しかし、法定休日の零時から24時をもって1日の休日とするというルールは、法令の原理原則が厳格に適用されます。
たとえば病院歯科の場合、勤務歯科医師の先生も当直に組み込まれることがあります。当直明けの9時から翌朝の9時までの24時間をもって休日としている医療機関が散見されますが、法定休日に関しては零時から24時までを1日として休日を付与しなければなりません。
法定休日の例外的な取り扱い

法定休日を与えなくてよい労働者
法定休日には例外があります。次の職種や職位の労働者に対しては、その業務が厳格な労働時間および休日の管理になじまないため、法定労働時間のケースと同様に、事業主および使用者は法定休日を与える義務はありません。
- 農林水産業に従事する者
- 管理監督者
- 機密の事務を取り扱う者(社長秘書など)
- 特殊な労働形態の者(監視・断続的労働に従事する者、宿日直勤務に従事する者)
農林水産業はその日の作業が天候に大きく左右されるため、働ける時に働き、それ以外は休みという就労パターンになりがちです。管理監督者は、自分がいつ、どれくらい働くかを自身の裁量で自由に決められるため、わざわざ法律で保護する必要がありません。
社長秘書など経営者と一体不可分な働き方を求められる職種は、一般の労働者のような勤務形態では仕事になりません。また特殊な労働形態とは、休憩と労働の明確な判別がつきづらい労働負荷の小さな業務(終日計器類を監視するような業務)に従事する労働者です。
法令休日に就業させる場合
法定休日に従業員を就業させる場合は、労働者の過半数代表者と時間外および休日労働に関する労使協定(36協定)を締結し、所轄の労働基準監督署へ届出する必要があります。
36協定の詳細については別の記事で改めて解説しますが、36協定を締結せずに従業員に法定休日出勤させると、労働基準法違反で厳しい罰則(懲役刑もしくは罰金刑)が科されます。例年多くの事業者が書類送検されていますので、くれぐれもご注意ください。
振替休日の制度もある
なお、法定休日を予め労働日と振り替えることで、法定休日労働を回避することができます。これは振替休日と呼ばれる制度で、法定休日を労働日に振り替えることで36協定の締結・届出が不要となり、法定休日割増賃金の支払いも不要となります。
ただし、法定休日に振り替えられた元々の労働日に従業員を就業させる場合には、やはり36協定と法定休日割増が必要となります。振替休日についても別の記事(時間外割増賃金)の中で改めて解説いたします。
年間休日は法定休日だけでよいのか?

法定休日と所定休日の違い
法定休日は、労働基準法などの労働法令に定められた事業主の義務であり、労働者の権利です。一方で、法定休日に加えて事業場が独自に定めた休日を所定休日といい、所定休日の付与は事業主および使用者の法令上の義務ではありません。
極論すると事業主や使用者は、従業員に対して法定休日さえ与えれば法令違反に問われることはありません。しかし、法定労働時間(1日8時間、1週間40時間※特例事業は44時間)を遵守するには、法定休日だけでは足りず、必然的に所定休日を付与することになります。
法定休日のみは労基法違反か?
少し本記事の趣旨から脱線しますが、法令で定められた最低限の休日のみとした場合(法定休日+労働基準法で定められた年次有給休暇の取得義務=年5日間)に、果たして1日あたりの労働時間が法定労働時間内に収まるのかどうか、シミュレーションしてみました。
- 与件
- 1年間(365日)=52週間
- 法定休日=52日間
- 年次有給休暇の取得日数(義務)=5日間
- 1週間の法定労働時間=40時間(特例事業=44時間)
- 計算
- 年間所定労働日数;365日ー(法定休日52日+年次有給休暇5日)=308日
- 週の所定労働日数;308日÷52週=5.9日
- 1日の所定労働時間;40時間÷5.9日=6.78時間(特例事業7.46時間)
事業主が必ず労働者に取得させなければならない年次有給休暇(5日間)を加えると、辛うじて法定労働時間をクリアできるようです。恐らく年次有給休暇の取得義務年5日間というのは、このあたりの計算を踏まえて設定された日数なのかもしれません。
ついでに前述のシミュレーションを踏まえて、1月あたりの所定労働時間が何時間になるのか計算してみました。
- 与件
- 年間所定労働日数=308日
- 1日の所定労働時間=6.78時間(特例事業7.46時間)
- 計算
- 通常の事業;308日÷12月×6.78時間=174.02時間
- 特例の事業;308日÷12月×7.46時間=191.47時間
週の法定労働時間40時間(特例事業は44時間)に52週を乗じ12ヶ月で除して求めた1ヶ月あたりの法定労働時間は173.3時間(特例事業は190.67時間)なので、法定休日+年次有給休暇(5日)だけでは、ちょっと過重労働になってしまいます。
1ヶ月の法定労働時間は法令に規定されていないので即違法というわけではありませんが、厚生労働省の令和6年版就労条件総合調査によると、全国の労働者の平均年間休日数は116.4日間です。さすがに年間休日が52日+有給5日では、スタッフは逃げ出してしまうでしょう。
法定休日のまとめ

私が就職したころの日本社会は「24時間戦えますか?」などといったキャッチコピーのCMが流行った時代で、プライベートを返上して仕事に励むのがビジネスマンの鏡とされていました。しかし、その後の平成不況やデフレ経済、リーマンショックなどを経て、人事評価の基準も勤勉さや協調性といった勤務態度から、効率性と具体的な成果に変容してきています。
また日本の労働生産性の低さは先進国の中でも際立っています。その主要因たるダラダラ残業は、積み残し雑務の消化試合に過ぎず、高付加価値を生み出すクリエイティブな時間などには決してなりません。むしろ、さっさとその日のタスクをこなし、職場を離れて自己研鑽に励み、明日の仕事に備えてリフレッシュした方がよほど職場の業績に貢献できるのです。
特にZ世代はタイパ(タイムパフォーマンス)を重視します。馴れ合い的な居残り残業が常態化し、職場の謎ルールに振り回されて合理的に仕事を進められない昭和の雰囲気が色濃く残る職場風土を忌避する傾向が強いです。自院の持続的な成長と発展のためには、従業員満足度を高める休日制度を確立し、ワークライフバランス実現を推進することが肝要でしょう。
お問い合わせはこちらから

リモートワークスコンサルティング社労士事務所


私たちは社労士事務所ですので就業規則や労使協定の作成および届出代行のほか、煩雑な社会保険や労働保険の事務代理もできます。オンライン特化型なのでスピーディでリーズナブル。電子申請に強く、SRP2認証も取得済みなので安全・安心です。
道内の開業医の先生であれば北海道中小企業総合支援センターの専門家派遣事業(公費による専門家派遣サービス)もご利用可能です。お問い合わせやお仕事のご依頼などは、こちらのフォームからお気軽にどうぞ(追って担当者からご連絡いたします)。



