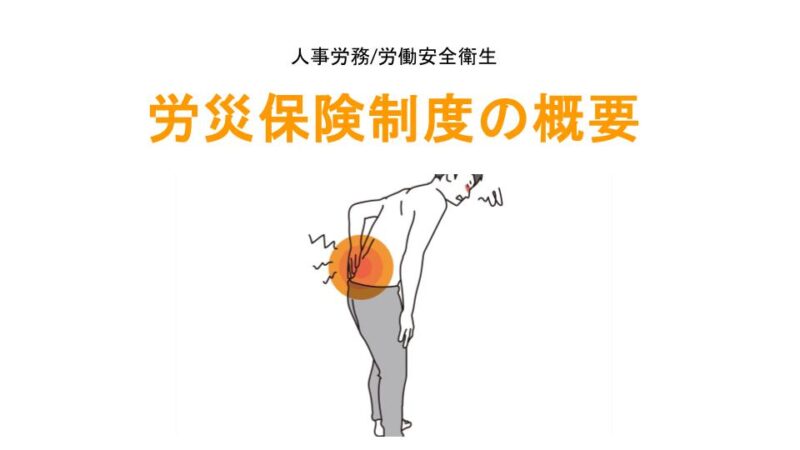
療養に関する社会保険制度
労災と私傷病
労働者が、病気になったり負傷して療養を受けようとする場合の公的保険には、労災保険と健康保険の2つがある。労災保険は、労働者が業務もしくは通勤に起因する傷病(労災)に対して保険給付を行い、健康保険は労災以外の私傷病に対する保険給付を行う。
保険の対象者
労災の加入対象は原則として労働者だが、一定の要件を満たす経営者や自営業者も特別加入できる。公的医療保険制度には、サラリーマンのための健康保険、自営業者のための国民健康保険、そして75歳以上の全国民を対象とした後期高齢者医療制度の3つがある。
公的医療保険制度には、上記のほかに公務員共済(国家公務員共済、地方公務員共済)と船員保険もあるが、本記事では解説を割愛する。
保険給付の内容
療養に関する保険給付
労災保険も公的医療保険も、疾病や負傷の治療のために要した医療サービス費用を、各種保険が負担してくれるものであり、これらの保険給付を療養給付と呼ぶ。療養給付は原則として医療サービスの提供(現物給付)によって行われるのが原則である。
上表によると、療養給付の内容は労災保険も公的医療保険も内訳の区分こそ違えど、全体的にはほぼ同一となっている。労災保険は原則として自己負担ゼロだが、公的医療保険は、加入している制度や被保険者の年齢・所得等によって、自己負担率が3割〜1割と異なる。
療養以外の保険給付
療養以外の主な保険給付には、傷病の療養のために休業している期間の生活保障として、労災保険には休業(補償)給付、傷病補償(給付)、健康保険には傷病手当金がある。また健康保険には、出産に対する保険給付があり、死亡に対しては両保険に給付金が用意される。
労災保険の休業(補償)給付と傷病(補償)給付の違いは、前者が短期休業に対する日払い給付、後者が長期休業に対する年金給付となっていること。国民健康保険と後期高齢者医療の任意給付は原則給付なし、例外的に給付可という意味で、法定任意給付はその逆である。
保険料の負担
労災保険料
労災保険料は、全額を事業主が負担し、賃金総額に業種ごとの保険料率を乗じて得た額を、一括納付する。なお労災保険は、労働基準法に定める事業主の労災補償義務を、労災保険が肩代わりするものなので、労働者を1人でも使用する事業場は強制加入となる。
医療保険料
健康保険料は、事業主と被保険者が折半して負担する。保険料は、被保険者ごとの標準報酬額に、都道府県別の保険料率を乗じて得た額を、翌月末日までに納付する。国民健康保険料と後期高齢者医療の保険料は、被保険者が全額を負担する。
療養に関する社会保険制度のまとめ
まずは社会保険の全体像をつかむ
医療保険といえば、健康保険や国民健康保険を連想する人が多いが、実は労災保険の療養給付は、これら公的医療保険の内容とほぼ同じである。また労災時は健康保険は使えないが、労災認定まで時間を要する場合には、いったん健康保険で医療機関を受診できる特例もある。
おすすめの書籍
障害年金や遺族年金では、労災保険と厚生年金保険が重複しており、多くの人には複雑でわかりづらいと感じるもの。本書は、社会保険料を払いたくない社員と労災にしたくない経営者を題材に、社会保険をわかりやすくユーモラスに解説したビギナー向けの一冊。

歯科クリニック/病院歯科に強い社労士事務所です。



🍀無料カウンセリングを受ける🍀
悩んだらまずはお気軽にお問い合わせください。
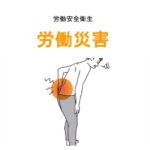

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/184edf1c.e9d12034.184edf1d.a75b57f0/?me_id=1213310&item_id=13097710&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F4808%2F9784534044808.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)
