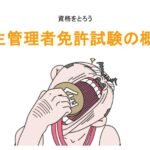労働安全衛生法について
労働安全衛生法の目的
労働安全衛生法は主要な労働法令のひとつである。同法では安全=業務上のケガ防止、衛生=健康障害の予防を意味しており、次の3つを柱としている。
- 職場における安全衛生措置の明示
- 職場における安全衛生責任の明確化
- 健康診断や安全教育など自主活動の促進
労働安全衛生法の業種分類
労働安全衛生法は、全ての労働者を対象とし、事業場単位で適用されるため、就業場所(本部、店舗、DC等)ごとに安全衛生管理者を選任することになる。なお業種によって労災リスクが異なるため、適用されるルールも異なる。
小売業における安全衛生管理者の選任
総括安全衛生管理者
総括安全衛生管理者は、次の事項について、安全管理者と衛生管理者を指揮監督する。
- 従業員の危険または健康障害を防止するための措置
- 従業員の安全または衛生のための教育・研修の実施
- 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置
- 労働災害の原因の調査および再発防止のための対策
- 職場の全従業員に対する安全衛生に関する方針の表明
- 職場の建物や設備の危険性および有害性の調査と対策
- 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価および改善
総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告(厚生労働省)
安全管理者
安全管理者は、労働者の負傷防止のために、常に事業場内を巡視し、次の事項を管理する。
- 職場の建物、設備、作業場所、作業方法に危険がある場合の応急措置・防止措置
- 安全装置、保護具その他危険防止のための設備・器具の定期的な点検および整備
- 作業の安全についての教育および訓練
- 発生した災害の原因調査および対策の検討
- 消防および避難の訓練
- 安全に関する資料の作成、収集および重要事項の記録
安全管理者選任時研修講習会のご案内(一般社団法人安全衛生マネジメント協会)
衛生管理者
衛生管理者は、労働者の疾病防止のために、毎週1回以上、事業場内を巡視し、次の事項を管理する。
- 従業員の危険または健康障害を防止するための措置
- 従業員の安全または衛生のための教育・研修の実施
- 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置
- 労働災害の原因の調査および再発防止のための対策
産業医
産業医は毎月1回または2ヶ月に1回の頻度で事業場内を巡視し、専門的・中立的な立場から次の事項を管理し、事業主に対して必要な勧告を行う。
- 健康診断、面接指導等の実施および従業員の健康保持のための措置
- 作業環境の維持管理、作業の管理など従業員の健康管理に関すること
- 健康教育、健康相談その他従業員の健康の保持増進を図るための措置
- 労働衛生教育に関すること
- 従業員の健康障害の原因の調査および再発防止のための措置
事業主(使用者)は、月々の時間外労働+休日出勤が、週80時間を超える労働者をリストアップし、産業医に報告しなければならない。
安全衛生推進者
安全衛生推進者は、総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者を選任する義務のない事業場のうち、従業員数10人以上の事業場において選任し、次の事項を管理する。
- 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること
- 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること
- 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること
- 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること
- 安全衛生に関する方針の表明に関すること
- 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること
労働安全管理体制のまとめ
安全衛生管理者が怠慢だったら
労災事故が多発している事業場において、総括安全衛生管理者が職責を果たしていない場合、都道府県労働局長は、事業主に対しその旨を勧告できる。また所轄労働基準監督署長は、安全管理者や衛生管理者の解任や増員を命ずることができる。
おすすめの書籍
衛生管理者免許には第1種と第2種があり、前者はすべての業種に対応している免許だが、後者は危険有害業務を除いた業種に限定される。小売業の場合、GMSなど屋内産業的工業的業種は第1種、食品SMなどその他の業種は第2種が必要となる。

歯科クリニック/病院歯科に強い社労士事務所です。



🍀無料カウンセリングを受ける🍀
悩んだらまずはお気軽にお問い合わせください。