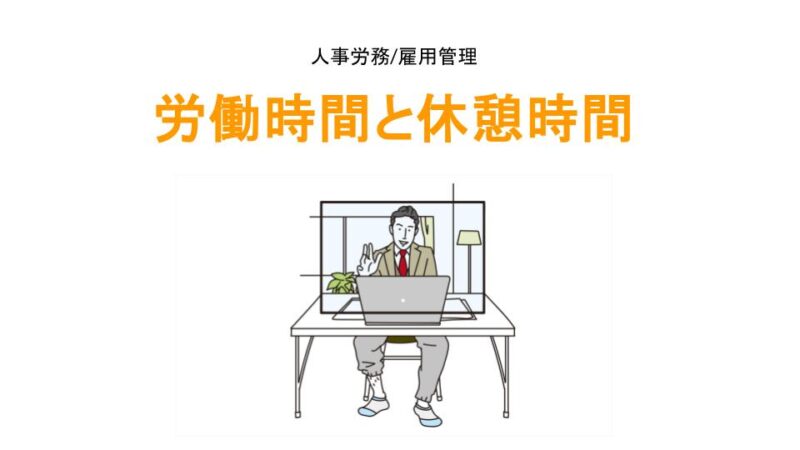
労働契約とはどのようなものか?
民法の契約と労働契約のちがい
労働契約とは、雇用に際して事業主と労働者の権利と義務を定めたものである。使用者は労働者から労働力を提供してもらう代わりに、その対価として賃金を支払う義務が生じる。一方の労働者は、賃金をもらう代わりに、契約に沿った労働サービスを提供する義務が生じる。
契約のルールは民法に規定されており、民法では契約自由(契約内容は当事者が自由に決めて良い)が原則だが、労働契約については、事業主の方が労働者よりも強い立場にあるため、事業主が労働者に不利な契約条件を強要しないように、労働法令で禁止事項を定めている。
労働契約法
労働基準法は、もともと民法の雇用契約に関する条項が独立分離して制定された法令だが、雇用形態の多様化により労働契約を巡るトラブルが頻発したことから、労働基準法における労働契約の原理原則や過去の労働裁判の判例をまとめ、平成20年に労働契約法が誕生した。
労働契約法には、労働契約を締結する際に、事業主と労働者が遵守すべき5つの原則が明記されている。
- 労使対等の原則
労働条件は事業主と労働者が対等の立場で交渉し合意にもとづき決定すること - 均等考慮の原則
労働条件は事業者と労働者の双方のバランスを考慮して決定すること - 仕事と生活の調和の原則
労働条件はワークライフバランスに配慮した内容であること - 信義誠実の原則
事業主と労働者は労働契約を信義に従い誠実に履行すること - 権利濫用禁止の原則
事業主と労働者は労働契約に定めた権利を濫用してはならないこと
なお、労働契約の内容を決める際は、労働基準法や労働契約法以外にも男女雇用機会均等法、障害者雇用促進法、高年齢者雇用安定法、パートタイム・有期雇用労働法、最低賃金法などもチェックしておく必要がある。
労働契約(契約の締結、労働条件の変更、解雇等)に関する法令・ルール
労働契約と労働条件通知書
労働契約は口頭でもOK!?
民法では契約は口頭のみで成立するとしているため、労働基準法や労働契約法にも契約書の作成義務は定められていないが、事後のトラブル防止のため、労働基準法では労働条件通知書の交付義務を、また労働契約書では書面による労働条件の明示努力をそれぞれ定めている。
労働条件通知書に記載すべき事項
労働条件通知書に明記すべき事項には、労働者に必ず書面で通知しなければならない絶対的明示事項と、その勤務先にて特定の労働条件を決める場合には、書面もしくは口頭で通知しなければならない相対的明示事項の2つがある。
絶対的明示事項(昇給の有無以外は必ず書面で通知)
- 労働契約の期間
- 有期契約の場合は更新の条件
- 就労場所と従事する業務内容
- 始業と終業の時刻、休憩時間、残業や休日出勤の有無
- 給与の決め方と計算方法および支給日
- 昇給の有無
- 退職に関する事項と解雇事由
相対的明示事項
- 退職金の支給対象者や支給額、支給方法
- 賞与の支給対象者や支給額、支給方法
- 労働者の費用負担
- 安全および衛生に関する事項
- 職業訓練の実施
- 業務災害時の補償および私傷病への扶助
- 表彰および懲戒
- 休職時の取り扱い
パートタイマーや契約社員への通知事項
パートタイム・有期雇用労働法では、パートタイマーや契約社員を雇用する場合、事業主は雇い入れようとする労働者に対し、前述の労働条件通知書に特定事項を追記したものを、交付しなければならないと定めている。
特定事項
- 昇給の有無
- 退職手当の有無
- 賞与の有無
- 雇用改善のための社内相談窓口
なお、事業主がいつでも人員整理できるよう短期の有期労働契約を反復更新するような契約は労働契約法で禁止されている。さらに労働基準法では、労働契約を3回以上更新もしくは1年以上にわたり継続雇用した労働者を雇い止めする場合は、解雇とみなすとしている。
労働契約のまとめ
昭和の曖昧な雇用慣行は通用しない
令和5年の労働基準法の改正により、入社後の人事異動の予定について、労働条件通知書に明記することが義務化された。昭和時代のように入社後の働きぶりをみながら”そのうち”処遇を決めるのではなく、人事制度において従業員のキャリアコースを整備しておかないと、有能な人材の獲得が難しい時代になった。
おすすめの書籍
労働条件通知書や労働契約書の無料フォーマットを活用する前に、労働契約の基本ルールくらいはしっかりと押さえておきたい。契約=法律行為であり、それぞれの契約条項とそれらの法的意味を正しく理解しておかないと、トラブルが発生した時に予期せぬリスクを招く。
[PR]RWCは人事業界の家庭医です。調子が悪いな…と感じたらお気軽にご相談ください。

🍀RWCならソレ解決できます🍀
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/184edf1c.e9d12034.184edf1d.a75b57f0/?me_id=1213310&item_id=16244662&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F1600%2F9784863191600.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)
