ちょっと独特な労働保険の徴収と納付

実は労働保険年度更新が苦手でした…
社労士の山口です。私が販売畑から人事部門に転身したのは三十路の頃で、一番初めに担当したのは給与計算業務です。給与計算では、社会保険料、雇用保険料、源泉所得税、個人住民税を月々の総支給額から控除するのですが、その後の扱いに苦戦したのが労働保険でした。
その理由は、社会保険料と源泉所得税および個人住民税は、給与や賞与を支給する都度、従業員ごとに計算して納付するのに対し、労働保険は年度更新という独特な方法で、一括処理していたからです。したがって会計処理も特異であり、私には苦手業務のひとつだったのです。
労働保険と社会保険の大きなちがい
すでに別の記事で詳細を解説していますが、社会保険料は毎月の給与を支払う都度、従業員ごとに徴収し、支払月の翌月末までに納付します。一方の労働保険(雇用保険+労災保険)は、事業場で1年間に支払った賃金総額を元に保険料を計算し、一括して納付します。
なお月々の給与から控除している雇用保険料の従業員負担分は、会計帳簿において預り金勘定でプールしておき、労働保険料を一括納付する際に、現金預金勘定と預り金勘定を相殺することになります(労災保険料の全額と雇用保険料の事業主負担分は法定福利費で計上)。
労働保険の年度更新とはどのような手続?

実は労働保険料は前払いが原則
毎年6月1日~7月10日までが労働保険の年度更新(確定申告)の提出期間となっています。労働保険料の独特な計算および納付方法は前述の解説でご理解頂けたのではないかと思いますが、なぜ労働保険料の納付を「年度更新」あるいは「確定申告」と呼ぶのでしょうか?
それは労働保険料は前払いの制度となっているからです。具体的には事業を開始すると50日以内に都道府県労働局に対して、翌年3月末までに支払う予定の賃金総額をもとに計算した概算労働保険料をいったん前払いし、翌年の年度更新期間に確定保険料と相殺する仕組みです。
基本的な考えは年末調整と同じ
以後は毎年6月1日から40日以内(要するに7月10日迄)に、前年度の概算保険料と確定保険料の相殺を行い、翌年度の概算保険料を納付する…というサイクルを繰り返します。これが労働保険料の納付を「年度更新」あるいは「確定申告」と呼ぶ理由です。
ちなみに労働保険では保険年度が4月1日~翌年3月31日までとなっています。これは社会保険も同様ですが、源泉所得税は1月~12月となっているため、混同しないように注意が必要です(年末調整=1~12月に控除した概算額と12月に確定した年調年税額を相殺する作業)。
労働保険料の納付方法

申告とあわせて保険料も納付する
労働保険料を申告したら、あわせて保険料を納付します。納付期日は労働保険料の申告期日と一緒ですので、確定申告は終えたのに、保険料の納付を失念してしまった…ということが起こると、場合によっては追徴金と延滞金が課される場合もあります(後述)。
労働保険料の納付は、原則として金融機関の窓口で行いますが、最近はペイジーが便利です。金融機関のATMあるいはインターネットバンキングから、簡単な操作で納付が完了します。なお可能なら口座振替をご利用下さい。引落日が納入期日後なので資金繰りに有利です。
延納制度で資金繰りがラクになる
労働保険料の納付については、一定の要件を満たせば3期に分割納付できる延納制度があります。従業員の多い医療機関では労働保険料が高額になり、借入が必要になるケースも珍しくありませんが、3期に分割納付することで、納税資金の調達コストを削減することができます。
| 延納期間 | 対象となる期間 | 納付期日 |
| 第1期 | 4月~7月 | 7月10日(年度更新の期日) |
| 第2期 | 8月~11月 | 10月31日 |
| 第3期 | 12月~3月 | 1月31日 |
年度更新をしないとどうなるか?
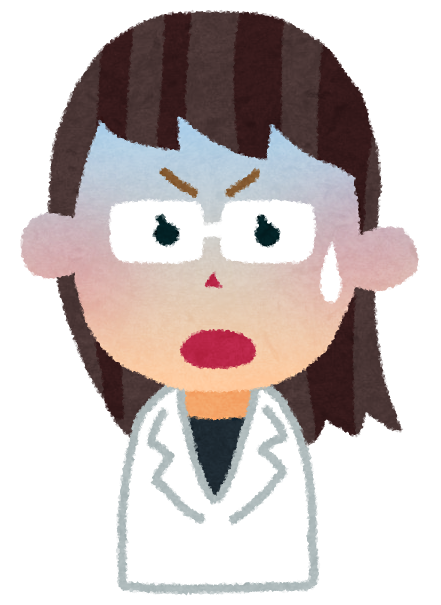
認定決定通知書とは?
労働保険料の年度更新を怠ったり、申告した額に不足があると、都道府県労働局の歳入徴収官から、認定決定通知書が送られてきます。認定決定とは、事業者が労働保険料を正しく申告しないので、行政が決めた額の保険料をいったん納付してください…という通知書です。
認定決定通知書とともに保険料の納付書が送られてきますが、この納付書は認定決定された保険料が、概算保険料なのか、確定保険料なのかによって異なります。前者は通常の納付書ですが、後者は納入告知書(督促状)となります。
確定保険料の認定決定は危ない
概算保険料が納付書なのに、なぜ確定保険料が納入告知書なのか?というと、概算保険料はあくまでも概算額の仮納付に過ぎませんが、確定保険料は本納付ですから、これに不足があったり、そもそも申告すらしないなどということは許されないからです。
ちなみに概算保険料の認定決定も、確定保険料の認定決定も、通知があった日から起算して15日以内に納付しなければなりません。特に確定保険料の認定決定も放置してしまうと、今度は追徴金(ペナルティ)と延滞金(遅延利息)が課されますので、くれぐれもご注意を。
おすすめの書籍
労働保険料の年度更新は、パート・アルバイトを含む全従業員の賃金総額を集計するところから始まります。医療業では出張医などが専門外来を担当することもあり、経営者が特別加入している場合は保険料の計算が複雑になりますが、本書は最新法令にもとづき、申告書様式の記入例も交えながらわかりやすく解説しています。

歯科クリニック/病院歯科に強い社労士事務所です。



🍀無料カウンセリングを受ける🍀
悩んだらまずはお気軽にお問い合わせください。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/184edf1c.e9d12034.184edf1d.a75b57f0/?me_id=1213310&item_id=21563203&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F0085%2F9784868210085_1_2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
