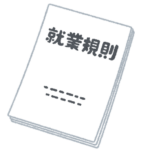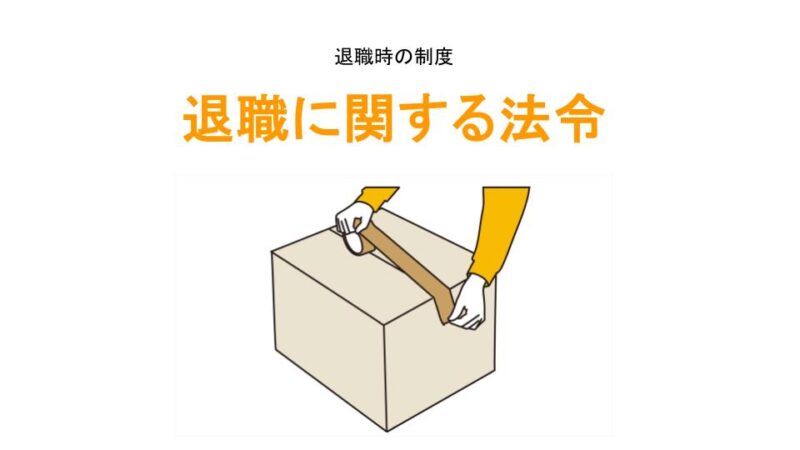
主な退職事由
定年退職
定年退職は、定年に達したことにより退職することをいう。高年齢雇用促進法では、事業主が60歳未満の定年制度を定めることを禁止しており、あわせて65歳まで、雇用継続や再雇用により、雇用を確保することも義務付けている。
自己都合退職
自己都合退職は、労働者が自らの意思によって退職することをいい、憲法の職業選択の自由や民法の雇用契約の解除権によって、自己都合退職する権利が保障されている。なお事業主からの一方的な雇用契約の解除(解雇)は、労働基準法により禁止されている。
契約満了による退職
契約社員が期間満了により退職することをいう。なお使用者が自由に雇用調整する目的で、短期の雇用契約を反復することは労働契約法で禁止されている。労働基準法は、契約を3回以上更新したり、1年以上雇用した労働者を雇止めすることを解雇とみなしている。
休職期間満了による退職
長期休業中の労働者が、休職期間が満了しても復職できない場合は、自然退職扱いとすることが多い。休職期間について法的な規定はないが、労災保険が給付される場合は療養開始から3年間で解雇でき、健康保険は復職の見込みゼロなら、資格喪失することになっている。
解雇
解雇を大別すると、労働者の非行によって懲戒解雇する場合と、経営不振によって労働者を整理解雇する場合の2つがある。解雇するには労働基準法にもとづき解雇する日の30日前に解雇予告をするか、解雇予告手当の支払いが必要となる。
解雇は労働者の経済生活を著しく脅かすため、労働基準法、労働契約法、男女雇用機会均等法などに、解雇制限もしくは解雇無効に関するルールが規定されている。
死亡退職
労働者が死亡した場合、労働契約は当然に解除される。労働者の死亡が労災事故による場合は、労災保険から遺族補償が行われ、また労災保険もしくは健康保険から、葬祭(埋葬)にかかった費用も給付される。
退職に関する法令
退職ルールは就業規則に明記する
労働基準法は、就業規則の絶対的必要記載事項と相対的記載事項を定めているが、退職は絶対的必要記載事項に該当するため、事業主は、それぞれの退職事由に応じて自社のルールを整備し、就業規則に明記しておく義務がある。
未消化の年次有給休暇はどうなる?
年次有給休暇は、労働者の疲労回復と健康的な生活の実現が目的なので、使用者が労働者の年次有給休暇を買い上げることは、労働基準法で禁止されている。ただし労働者が退職日までに、残った年次有給休暇を取得できない場合に限り、買い取りが認められる。
未払賃金があるとき
退職後も未払賃金がある場合、労働者は使用者に対して、賃金支払確保法にもとづき、年14.6%の遅延利息を請求できる(退職金除く)。なお、未払賃金および退職金の請求権は、支給日の翌日から5年間(賃金は当面3年間)経過すると時効により消滅する。
受給中の保険給付はどうなるか?
労災保険から療養や休業に対する保険給付を受けている者が退職しても、受給権は消滅せず、退職後も保険給付される。健康保険証で通院中の場合は、転職先の健康保険に再加入するか、あるいは国民健康保険に加入しなければならない。
健康保険の任意継続
退職した労働者の年収によっては、国民健康保険に加入するより、前職の健康保険を継続した方が保険料を低く抑えられる場合もある。そのような時に、一定要件を満たした労働者に限り、2年間という期限つきで、前職の健康保険を任意継続できる制度もある。
退職に関する各種証明書
労働基準法により、使用者は、労働者が自身の退職に際して、次の事項について証明書を請求した場合は、遅滞なく労働者に交付する義務がある。
- 勤務期間
- 業務内容
- 職位
- 賃金
- 退職事由
あわせて使用者は、雇用保険法にもとづき、所轄のハローワークに、退職者の雇用保険資格喪失届とあわせて離職証明書(および退職者が希望した場合は離職票)を提出する義務もある。
退職に関する法令のまとめ
退職ルールこそ明確にしておく
これまで退職に関する主な法令や制度について解説してきたが、他にも社会保険料や住民税の一括徴収、貸与物の返還、社宅の引き渡し、競業避止義務など、考慮すべき点は多岐にわたる。ゆえに退職ルールこそきちんと整備し、就業規則に規定しておく必要がある。
おすすめの書籍
情報漏洩や従業員の競業などからいかに自社を防衛するか、また競業他社からの人材引き抜きにどう対処するかについて、弁護士が指南する経営法務の実務書。販売職にはかなり重たい内容だが、GMSの店長(事業部長)クラスなら、ぜひ一度は読んでほしい。

歯科クリニック/病院歯科に強い社労士事務所です。



🍀無料カウンセリングを受ける🍀
悩んだらまずはお気軽にお問い合わせください。