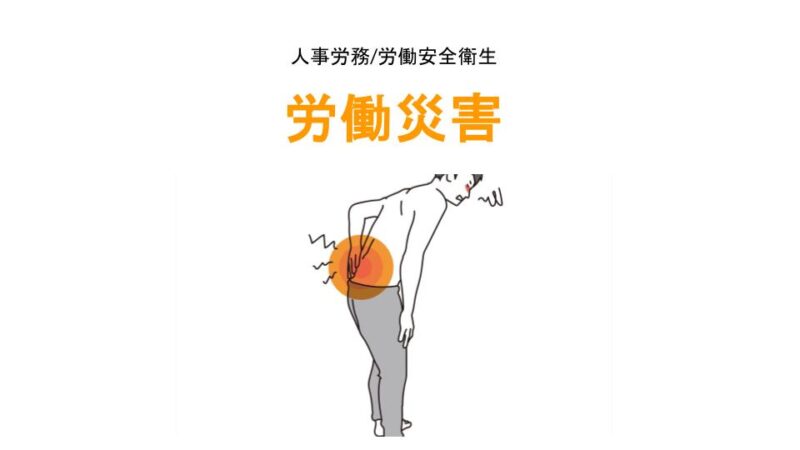
休日と休暇・休業のちがい
休日とは?
労働者が長い職業人生を全うするには、健康かつ文化的な生活が保障されねばならない。ゆえに労働基準法では、休日や休暇・休業などを定め、これらを労働者の権利としている。このうち休日は労働義務の無い日をいい、事業主が労働者を休日労働させると違法となる。
休暇と休業
休暇や休業は、特定の労働者について、労働日における労働義務を免除する日をいう。大雑把に例えると、休日は事業場そのものが休業しており、全ての労働者が就業していないが、休暇や休業の場合、事業場は営業していて、他の労働者は働いているということである。
主な休日
法定休日と所定休日
労働基準法は、事業主に対し、1週間に1日以上もしくは4週間に4日以上の法定休日を労働者に与えることを義務付けている。一方の所定休日は、事業主が任意に付与する休日であり、法的ルールはない。なお令和5年度の法定休日+所定休日の労働者平均は115. 6日である。
振替休日と代休
振替休日は、事前に法定休日と労働日を入れ替えることであり、代休はいったん法定休日に労働させてから、事後に代休を与えるものである。振り替えた労働日の割増賃金は不要だが、代休の場合はすでに法定休日労働しているため、割増賃金の支払いが必要である。
主な休暇
年次有給休暇
労働基準法は、雇入れ後6ヶ月を経過し、その期間の所定労働日の8割以上出勤した労働者に対し、年10日以上の年次有給休暇を与えることを、事業主に義務付けている。年次有給休暇は労働者の法的権利なので、取得にあたって使用者の承認は不要である。
子の看護休暇と介護休暇
育児介護休業法により、未就学児を養育する労働者や家族を介護する労働者は、子の看護もしくは家族の介護のために、年5日間の看護休暇あるいは介護休暇を取得できる。これらの休暇も法律上の労働者の権利なので、取得にあたって使用者の承認は不要である。
生理休暇
労働基準法は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求した場合に、その女性を就業させることを禁止している。生理休暇の取得にあたって医師の診断書等は不要で、休暇は半日単位や時間単位で付与することもできるが、取得日数に上限を設けることはできない。
代替休暇
代替休暇とは、月60時間を超えて法定時間外労働をした場合の上乗せの割増賃金に代えて、年次有給休暇とは別に有給休暇を付与できる制度である。例えば月60時間超の残業が10時間なら、割増手当に代えて10時間÷割増率25%=2.5時間の代替休暇を付与してもよい。
主な休業
産前産後休業
労働基準法は、出産予定日から6週間前および出産日から8週間を経過しない女性を労働させることを禁止している。なお産前については、本人が就業を希望すれば休業させる義務は無いが、産後については原則として本人の意向に関わらず就業禁止となっている。
育児介護休業
育児介護休業法では、1歳未満の子を養育する労働者は子が1歳に達するまで、また家族を介護する労働者は最長で93日間まで、それぞれ育児休業もしくは介護休業をすることができる。育児介護休業は男性も可能であり、また法定の権利なので使用者の承認は不要である。
労災による休業
労災で休業した時の休業補償や休業給付は労働基準法や労災保険法に規定されているが、労災時の休業ルールは存在しないため、労災申請は行うが休業させないという悪質な使用者が問題になっている。こんな場合は労働契約法の安全配慮義務違反で労基署に相談すればいい。
会社都合の休業
労働基準法では、会社都合により、使用者が労働者に自宅待機を命じる場合には、事業主は労働者に平均賃金の6割以上の休業手当を支払う義務を定めている。また労働者は民法にもとづき、本来受け取るはずだった賃金の全額の支払いを使用者に請求することもできる。
休日と休暇・休業のまとめ
理解を深めてトラブル予防
休日と休暇・休業は類似したワードだが、①休日は法令上の労働者の権利、②休暇は労働者の権利に属するものと、事業主が任意で与えるものがあり、そして③休業は就業を禁じる(免除する)もの、ということを理解せず運用を誤ると、思わぬトラブルに発展する恐れがある。
おすすめの書籍
筆者も経験があるが、クリエイティブな思考はオフラインから生まれることが多い。日々の作業に忙殺され、休日返上で働いてばかりいると、いつしか自身の知識やスキル、思考が陳腐化して、自ら人材マーケットでの市場価値を下げてしまう。オンとオフのメリハリが大事。

歯科クリニック/病院歯科に強い社労士事務所です。



🍀無料カウンセリングを受ける🍀
悩んだらまずはお気軽にお問い合わせください。


![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1863b02b.4de5dfb0.1863b02c.ab7e73e2/?me_id=1278256&item_id=24062778&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frakutenkobo-ebooks%2Fcabinet%2F3138%2F2000016283138.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)
