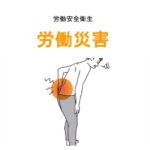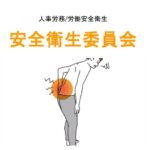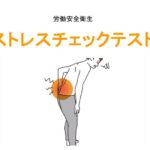障害(補償)等給付とは?
障害による逸失利益を補償する制度
労働者が労災によって障害状態になると、以後の就業が不能となったり、あるいは著しい制限を受けることになり、賃金獲得能力を大きく喪失してしまう。このような場合に、被災労働者の逸失利益を補償するために、労災保険から保険給付が行われる。
障害(補償)等給付はいくらもらえるのか?
障害(補償)等給付は、障害の度合いに応じ第1級〜第14級に区分され、障害の重い第1級〜第7級までは障害(補償)等年金、第8級〜第14級は障害(補償)等一時金が給付される。給付額は、年金あるいは一時金の給付基礎日額に、表の所定日数を乗じて得た額となる。
厳密には業務災害によるものを障害補償等給付、通勤災害によるものを障害等給付というが、本記事では障害(補償)等給付のように、ひとくくりにして解説する。
複数の障害があるとき
同一の労働者が、複数の障害(労災に起因するものに限る)を有する時は、障害の発生要因と、障害の部位によって、原則として次の3パターンのいずれかで保険給付を行う。
■併合(併合繰り上げ)
同一の労災事故により、複数の部位に障害が残ってしまった場合は、重い方の障害等級を適用する。なお障害の度合いにより、重い方の障害等級をさらに1〜3級繰り上げる。
■加重障害
複数の労災事故により、同一の部位の障害状態が悪化してしまった場合は、最初の労災保険給付を継続したまま、障害が新たに加重した部分について、保険給付の上乗せを行う。
■複数の保険給付
複数の労災事故に遭い、それぞれ別の部位に障害が残ってしまった場合は、それぞれの部位に応じた労災保険給付を、それぞれ個別に行う(同一人に複数の保険給付を行う)。
急に障害状態になってしまったとき
労災事故に遭った労働者が、ある日突然収入を絶たれ、経済的に困窮してしまうことの無いように、障害(補償)等年金については、年金を前払いしてもらえる制度がある。前払一時金の額は、障害等級ごとに上限が定められており、上限は概ね年金の4.3ヵ年分となっている。
障害(補償)等給付に関連した制度
障害特別支給金
労災保険制度は、保険本体部分と被災労働者の社会復帰等を支援するための付帯事業の2本立てとなっており、後者の代表的な制度が、特別支給金である。
障害(補償)等給付の場合は、障害等級に応じた障害特別支給金と障害特別年金・一時金が、通常の保険給付に上乗せされる。なお障害特別支給金は等級に関わらず一時金にて給付され、障害特別年金・一時金は算定基礎日額(賞与の1日あたり平均額)により計算される。
障害(補償)等給付は給付基礎日額(≒平均賃金)で計算するが、労災保険料は賃金総額(賞与込)をもとに徴収されるため、特別年金・一時金で還元するしくみである。
傷病(補償)等年金
傷病(補償)等年金は、休業(補償)等給付の受給から1年6ヶ月経過(長期化)し、傷病等級第1〜3級に該当(重症化)した場合に、休業(補償)等給付から切り替わるものである。給付額は傷病(補償)等年金と同額で、主な違いは障害確定(症状固定)か療養中かである。
障害厚生年金と障害基礎年金
障害になると、障害厚生年金と障害基礎年金からも、保険給付が行われる。これら社会保険からの給付は、障害の原因が労災か私傷病かを問わない。また一定要件を満たす扶養家族がいる場合には年金が加算されるが、労災保険に比べて給付のための要件が細かく定められている。
社会保険からも障害年金が給付されたとき
前述のとおり、厚生年金保険や国民年金の障害年金は、給付事由を問わないため、労災保険と社会保険の障害年金が併給されることもある。この場合、社会保険の給付内容に応じて、労災保険の側が減額調整されて給付される。
障害(補償)等給付のまとめ
障害は身体障害だけではない
小売業では、重篤な労災事故が発生するケースは少ない。だからといって障害(補償)等給付は他人事などと安易に考えてはいけない。なぜなら障害には精神障害も含まれ、職場のハラスメントや過重労働による精神疾患が労災認定されるケースが増えているからだ。
おすすめの書籍
小売業は労働集約型かつ長時間労働時間という特徴ゆえに、職場の人間関係や過重労働による精神疾患および労災リスクが比較的高い業種といえる。本書はどのようなケースが労災認定されるのか、判例をもとにわかりやすく解説し、企業はいかに対応すべきか教示してくれる。

歯科クリニック/病院歯科に強い社労士事務所です。



🍀無料カウンセリングを受ける🍀
悩んだらまずはお気軽にお問い合わせください。